OKY/おまえ、ここに来て、やってみろ?
JSHRMで担当しているグローバル活動事業の一環として開催したセ



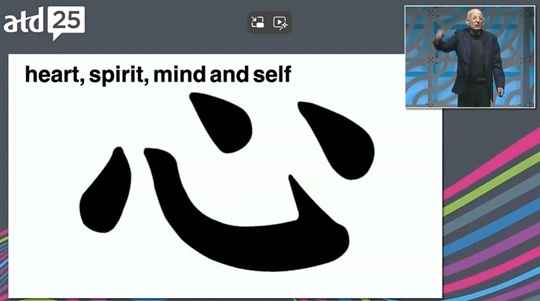
キーノート、ラストは、セス・ゴーディン(Seth Godin)。
メタファーがミルフィーユみたいに畳みかけられる。こんなアートなプレゼンは初めてです。
【超抜粋】![]() パート1/6:開会の挨拶〜「意義ある仕事」の導入
パート1/6:開会の挨拶〜「意義ある仕事」の導入
省略
________________________________________
![]() パート2/6:Seth Godin登壇〜「意義ある仕事」の本質とは
パート2/6:Seth Godin登壇〜「意義ある仕事」の本質とは
おはようございます!5月ですからね、まずはゴルフの話をしましょうか。…ゴルフって、観戦するには最悪のスポーツだと思いませんか?その理由は2つあります。
1つ目は、何も起きない。そして2つ目は、もし何か良いことが起きても、思いきり拍手することが許されない。
代わりに、あの小さなゴルフ拍手をしなきゃいけないんです(笑)。ではまず、最悪なゴルフ拍手から始めましょう![]()
もっと大きく![]() さらに
さらに![]() もう一回
もう一回![]() いいですね!ありがとう!
いいですね!ありがとう!
実はこれは、組織の中で私たちがやっていることのメタファーなんです。ちいさな「つながりの芽」「関心の糸」を見つけて、それを増幅して、仲間と一緒に広げていく。まさに私たちの仕事の姿です。
________________________________________
さて、ここでちょっとやってみてください。
右手をできるだけ高く挙げてみてください。
ありがとうございます。では……さらにもう少し高く!
――どうして今、それができたんでしょう?
実は私たちって、常に“まだ出し惜しみしてる”状態なんです。
なぜなら、人生の中でずっと「もっとやれ」「まだやれる」と言われてきたからです。親に。体育の先生に。英語の先生に。上司に。ずっと。だから、最初から本気は出さない。全力を求められるかも、と構えてしまうんですね。
________________________________________
「最高の仕事」は、出し惜しみしなかった時に起きている
少し考えてみてください。
あなたが今まで経験した「最高の仕事」って、どんなものでしたか?
誰に聞いても、その「最高の仕事」は違います。職種も業界もバラバラ。正解なんてない。でも、共通しているのは、そこに“何か特別な感覚”があったことです。
私は90か国、1万人以上にアンケートをとりました。「最高の仕事とは何か?」
まず最初に、よくある“上司目線の要素”――
昇進できる/人に指示できる/クビにならない――を並べてみました。でも、それだけでは全く足りませんでした。
________________________________________
彼らが口にした「本当に大切なもの」はこうでした:
• ![]() 成し遂げたという感覚(Accomplishment)
成し遂げたという感覚(Accomplishment)
• ![]() 自律と選択の自由(Independence)
自律と選択の自由(Independence)
• ![]() 尊重されること(Respect)
尊重されること(Respect)
これらがそろったとき、
人は「これは、人生で一番良い仕事だった」と感じるのです。
________________________________________
![]() パート3/6:ミツバチの「成長の歌」と、リーダーが果たすべき役割
パート3/6:ミツバチの「成長の歌」と、リーダーが果たすべき役割
さて、ここで「Song of Increase(成長の歌)」という、私が大好きな話を紹介します。これはジャクリーン・フリーマンという著者から学んだものです。
5月、北アメリカ。ミツバチたちは長い冬を越えて、ようやく春を迎えます。巣は傷んでいて、ギリギリ生き残った状態。女王蜂は見た目“リーダー”ですが、実際に命令を出しているのは働きバチ(メイデン)たちです。彼女たちが「今、女王に卵を産ませる時だ」と指示を出します。
________________________________________
![]() そしてある時、奇跡のような出来事が起きる
そしてある時、奇跡のような出来事が起きる
巣が十分に回復し、ハチミツが蓄えられたその時――
女王蜂とすべての大人の働きバチたちが、一斉に巣を離れるのです。彼女たちは空へと飛び立ち、「Song of Increase(成長の歌)」を歌いますそれはまるで、空に向かって未来に賭ける歌。
彼女たちは3日以内に新しい場所を見つけないと全員死にます。
でも、それでも彼女たちは飛び立つのです。
そして、彼女たちが残していくのは:
• 新しく生まれる幼虫たち(次世代)
• 新しい女王蜂
• そして、巣いっぱいのハチミツ
これは、「命がけで未来を渡す」「次の世代へ意義を託す」行為。この歌を聞いた人は、決して忘れることができないと言われています。
________________________________________
![]() リーダーの役割とは、「意義の歌」を歌う空間をつくること
リーダーの役割とは、「意義の歌」を歌う空間をつくること
私たち、組織の中のリーダーや教育者、人事担当者は、
「Significance(意義)」の歌を歌える場をつくることができるんです。
つまり、単に働くのではなく、
![]() 「意味のある仕事を共にする」
「意味のある仕事を共にする」
![]() 「自分がここにいてよかったと思えるような体験」
「自分がここにいてよかったと思えるような体験」
を可能にする空間を築くことです。
________________________________________
![]() それを実現するには、時に「型破り」が必要
それを実現するには、時に「型破り」が必要
ある自転車レースで、最後尾の選手がとった行動を紹介します。
彼は常識にとらわれず、全く新しい空気力学の姿勢で走りました。
誰もが笑ったけど――彼の挑戦が、新たな流れをつくったのです。
これは、組織の中でも同じ。
「マニュアル通りにやること」に慣れていると、革新は生まれません。
でも、時に誰かが「違うやり方をしてみよう」と動くことで、
組織全体が次のステージに行けることがある。
________________________________________
![]() もうやめよう、「椅子取りゲーム」
もうやめよう、「椅子取りゲーム」
皆さんご存じの通り、椅子取りゲームは「誰かを排除する」仕組みです。
• 9人のプレーヤーに、椅子は8脚。
• 音楽が止まると、誰か1人が座れず“脱落”。
これはまさに、多くの組織で行われていることの象徴です。
「限られたポスト」「限られたリソース」に人々が群がり、
協力よりも競争が先にくる。
でも、社員が望んでいるのは――
希少性(Scarcity)ではなく、豊かさ(Abundance)なんです。
________________________________________
![]() 次につながるキーワード:「5つの行動指針」
次につながるキーワード:「5つの行動指針」
Sethは、このようにまとめました:
1. これは「未来に向けた選択」である(AIや世代交代の中で)
2. 「管理者」ではなく「リーダー」になることが求められている
3. 曖昧さや葛藤に向き合うスキルが必要になる
4. 責任は自ら引き受け、成果は他者に渡す
5. 「本気でやる」か、それができないなら「やめる」勇気を持つ
________________________________________
![]() パート4/6:Interface社の変革と、「Page 19」を書く人になる
パート4/6:Interface社の変革と、「Page 19」を書く人になる
![]() 「あなたは交通渋滞に“巻き込まれている”わけではない」
「あなたは交通渋滞に“巻き込まれている”わけではない」
まず、こんな言葉から始まります。
「あなたは交通渋滞に巻き込まれているのではない。あなたが“交通渋滞”なのだ。」
つまり、「状況の犠牲者」をやめよう、ということです。
私たちはよく「この状況では仕方ない」「できる限りやった」と言いますが実際には、自分自身がその“状況”を形づくっているんです。
________________________________________
![]() Interface社の実話:世界で最も汚い産業から、サステナビリティの象徴へ
Interface社の実話:世界で最も汚い産業から、サステナビリティの象徴へ
Ray Andersonという人物がいます。彼は30年前、自社のカーペット会社(Interface)が世界で最も環境に悪い企業の1つだと気づきます。その後、幹部6人を部屋に集め、こう言いました:
「10年以内にカーボン・ニュートラル(炭素排出ゼロ)を実現し、その後は“カーボン・ネガティブ”を目指す。」
幹部たちはパニックに陥りました。「私たちは、ただのカーペット屋ですよ!?そんなの無理です」と。でもRayは言いました。
「やり方は分からない。でも、私は君たちをサポートする。」
この一言が、変革のすべての始まりでした。株価も伸び、従業員は口を揃えて言いました:「これは、私の人生で最高の仕事だった。」
________________________________________
![]() “Page 19 Thinking”:未完成ページの筆者になる勇気
“Page 19 Thinking”:未完成ページの筆者になる勇気
Sethが主導したもう一つのプロジェクトが『Carbon Almanac(カーボン年鑑)』です。
世界90か国、1,900人の共同執筆者で、9.7万語の本を5か月で作り上げました。しかも、指示役はいない。
Sethはこう伝えました:「この本の“Page 19(19ページ)”はまだ白紙だ。誰かが下書きを書く。そして、誰かがそれを改良する
それは“失敗”ではなく、“先へ進める土台”なんだ。」
つまり、「未完成の何かを恐れずに書き出す人になる」――それが、リーダーシップの始まりなんです。
________________________________________
![]() 「責任を引き受け、功績を譲る」文化を
「責任を引き受け、功績を譲る」文化を
組織が変わるには、この姿勢が欠かせません:
• 責任は自分がとる
• 成果や手柄は、他人に譲る
これが実現できると、組織は協力しあい、豊かさが循環する場になります。もう椅子取りゲームは必要ありません。
________________________________________
![]() 「マップではなくコンパスを渡す」組織設計
「マップではなくコンパスを渡す」組織設計
典型的なピラミッド型の「指示伝達型組織」は、
最前線の人たち(接客、製造など)にまったく裁量を与えません。
でも例えば、リッツカールトンでは:
• 清掃スタッフにも2,000ドルまでの裁量権が与えられている(お客様の満足のためなら、即決OK)
これは「地図を渡す」のではなく、“目的地の方向(コンパス)を示して、進み方は任せる”というやり方です。
「信頼できないから与えられない」というなら、それは組織側の問題です。
________________________________________
![]() “人は機械の部品ではない”という真実
“人は機械の部品ではない”という真実
企業の組織図には、よく小さな四角が並びます。
それは、「誰でもその枠に当てはめられる」ことを意味しています。でも本来、人は唯一無二の存在です。彼らの仕事には「署名(サイン)」が必要です。
________________________________________
![]() パート5/6:リアルスキルとは?|態度×緊張感が文化を変える
パート5/6:リアルスキルとは?|態度×緊張感が文化を変える
![]() 決断=成果じゃない。“良い判断”と“良い結果”は別物
決断=成果じゃない。“良い判断”と“良い結果”は別物
Sethの問いかけ:
「この半年で、良い判断をひとつでもしましたか?」
→ 多くの人が手を挙げる
「では、その判断は良い結果になりましたか?」
→ みんな「YES」と思う
でもそれ、本当に関係ある?たとえば、宝くじを買って当たったら“良い判断”だった?
…ちがう。
「判断の質」と「結果」は別の話なんです。私たちは「結果」に依存しすぎると、決断することそのものを恐れるようになります。
________________________________________
![]() ゴルフ型人材 vs サーフィン型人材
ゴルフ型人材 vs サーフィン型人材
• ゴルフ型:変化なし。条件も動かない。ちょっとずつスコアを縮める。
• サーフィン型:毎回違う波。波を「選ぶ力」こそが重要。
これからの時代に必要なのは、波を見て、動ける人材です。つまり、「ルールをこなす人」ではなく「変化を起こす人」。
________________________________________
![]() 責任を引き受け、功績を与える文化を築こう
責任を引き受け、功績を与える文化を築こう
こんなシンプルな原則をSethは提示します:
Take responsibility, give credit.
(責任は自分が引き受け、手柄は他人に)
これができる組織は、ミュージカルチェア(椅子取りゲーム)をやめて、「余白がある・豊かさがある」チームに変わっていけます。
________________________________________
![]() 本当の共感:「実用的な共感(Practical Empathy)」
本当の共感:「実用的な共感(Practical Empathy)」
「相手の立場に立つ」って、よく聞きますよね。
でも本当はこうなんです:
![]() 「私があなただったらこうする」
「私があなただったらこうする」
![]() 「私はあなたじゃない。あなたがあなたであることを、私は理解しようとする」
「私はあなたじゃない。あなたがあなたであることを、私は理解しようとする」
この「実用的な共感」が、真にエネルギーある組織を育てます。
Dorothyを助けたTin Manもライオンも、最初は自分のために旅に出た。でも旅の中で、他者のことを考えるようになった――そんな物語と同じです。
________________________________________
![]() Inuksuk(イヌクシュク):存在の証を残す
Inuksuk(イヌクシュク):存在の証を残す
これはカナダの先住民の文化で、石を積んだ道しるべです。
「ここに人がいた」「そして、この先へ進んだ」
組織においても、人がその仕事に“署名”できるかが重要です。人は“入れ替え可能な部品”ではない。その人がいたという痕跡が、文化になる。
________________________________________
![]() 緊張感(Tension)=成長のための摩擦
緊張感(Tension)=成長のための摩擦
Sethは言います:
ストレスではなく、緊張感を持て。
• ストレス=同時に2つを求めてパンクしそうになる状態
• 緊張感=「このバンドを引けば、次の音が出る」ような創造的な摩擦
音楽も演劇も、緊張感があるからこそ、魅力がある。職場も同じ。「摩擦のない職場」では、誰も挑戦しなくなる。
________________________________________
![]() リアルスキルとは何か?
リアルスキルとは何か?
あるインターンの集まりで、Sethは言います:
「今からチームを組んで、ビル・ゲイツのプロジェクトに取り組む。あなたがリーダーなら、誰を選びますか?」
そのとき、誰もが選ばれる側としての自分を意識しました。
そしてこう問われました。「6週間前、ここに来たときから“選ばれる自分”でいようとした?」
→ していない。
でも、人生って実はずっと椅子取りゲームなんです。
________________________________________
![]() 「LinkedInに書きたい人材像」を自分が体現できているか?
「LinkedInに書きたい人材像」を自分が体現できているか?
• 正直さ
• 誠実さ
• 革新性
• 他者への共感
• ポジティブな影響力
このリストの多くは、「才能」じゃなくて「態度」。
そして態度はスキル。学べるし、育てられる。
![]() Zig Ziglarの言葉:
Zig Ziglarの言葉:
GAS=Gifts(才能)・Attitude(態度)・Skills(技能)
本当に大事なのは、Attitude。
そしてそれは、鍛えられる。
________________________________________
![]() パート6/6:採用の再定義と、月に残る足跡の話
パート6/6:採用の再定義と、月に残る足跡の話
![]() 採用を「面接ゲーム」から解放せよ
採用を「面接ゲーム」から解放せよ
多くの企業がまだこう考えています:
「うちの採用は、面接を通じて“良さそうな人”を選ぶんだ」
でも、Sethは問いかけます。
![]() 「面接が上手=良い社員」ではない
「面接が上手=良い社員」ではない
![]() 「印象が良い=仕事ができる」ではない
「印象が良い=仕事ができる」ではない
なぜなら、**面接は“一度きりのショー”**だから。
現実にはもう二度と同じ「面接」を仕事ですることはない。
________________________________________
![]() Greyston Bakeryの実例:「オープン・ハイヤリング」という革命
Greyston Bakeryの実例:「オープン・ハイヤリング」という革命
ニューヨーク州ヨンカーズにあるベーカリー「グレイストン」では、こんな採用をしています:
• 応募者は、名前と電話番号をクリップボードに書くだけ
• 空きが出たら、順番に雇用
• 2週間のトレーニング後、仕事を続けられるなら採用完了
結果はどうなったか?
![]() 離職率が他社より圧倒的に低い
離職率が他社より圧倒的に低い
![]() 生産性・顧客満足も高い
生産性・顧客満足も高い
![]() 採用にかかる“偏見”が排除され、機会が均等に
採用にかかる“偏見”が排除され、機会が均等に
その後、ボディショップ社でも同モデルを導入。離職率が60%減!
________________________________________
![]() 「文化づくり」こそが、人と人を惹きつける
「文化づくり」こそが、人と人を惹きつける
優秀な人は、“一番給料が高い職場”ではなく、「自分の存在が大切にされる職場」に惹かれる。
• 尊重されること
• 目的に向かって共に歩めること
• 自分が“この仕事に名前を刻める”こと
________________________________________
![]() 月に残された足跡の話(最終章)
月に残された足跡の話(最終章)
Sethがある夜、家族と共にニューメキシコのイベントに招待されました。
寒空の下、毛布にくるまり、丘の上の焚き火の周りにいたその場で―スピーカーとして登場したのは、あのニール・アームストロング。
その夜、満月が彼の肩越しに昇り始めたとき、彼はこう言いました:「私は、あそこへ行ったことがある。」
そして彼が撮ったあの写真には、月面に“足跡”が残っていた。
NASAがそれを成し遂げた当時、彼らの計算能力は今私たちのスマホ以下。
________________________________________
![]() 私たちの仕事にも、足跡を残す意味がある
私たちの仕事にも、足跡を残す意味がある
Sethのラストメッセージ:
「私たちがここにいる理由は、“株主に3セント多く稼がせる”ためじゃない。私たちは、“意味のある仕事”のためにここにいる。」
「目的(Purpose)とは、一時の成果のためでなく、時間を超えて続く機能性のことだ。」
________________________________________
![]() クロージング・メッセージ
クロージング・メッセージ
Sethの友人Challenの言葉:
「この部屋にいる全員は、すでに成功している。
では、私たちは“意味ある存在であろう”と願えるか?」